12月の行事 大晦日 12月31日

1年の最後の12月31日は、古い年から新しい年へと移る年越しの日。大掃除の締めくくりとなる「掃き納め」や、おせち料理づくりなどでお正月の準備を整え、家族で集まって年越しそばを食べてお正月を迎えます。
昔は数え年であったため、年を越すと年齢が1つ増えました。そのため年越しのことを「年とり」ともいいます。
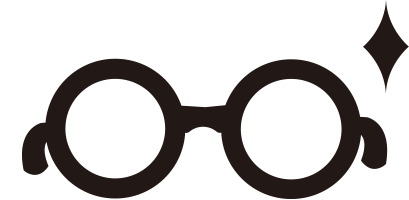 このページの見どころ!!
このページの見どころ!!
大晦日の由来

月の末日を「晦日(みそか)」といい、1年の最後の晦日である12月31日を「大晦日(おおみそか)」といいます。
旧暦では1日の始まりを日没としていたので、大晦日の夜は新年の1月1日(元日)となり、お正月の神様である「年神様」が訪れるのも大晦日の夜とされています。昔は「年ごもり」といって大晦日の夜から元日の朝にかけて神社や寺院にこもって徹夜で年神様を迎える風習があり、「年越しの夜は眠ってはいけない」といわれていました。早く寝てしまうとシワが増える、白髪になるといった伝承も各地に残っています。
 ちょこっとメモ!
ちょこっとメモ!
大晦日の風習あれこれ
年越しそば

大晦日の夜に家族でいただく年越しそばは、江戸時代から続く風習です。細く長いそばは長寿の象徴であり、薬味のネギにも「ねぎらう」という意味があります。年越しそばは縁起物なので、年を越してから食べたり、残したりするのは縁起が悪いとされています。
年とり魚

無事に年越しを迎えることができたお祝いに、「年とり魚」を食べる習慣も各地に残っています。年とり魚は西日本ではブリ、東日本では鮭のことが多く、地域によっては鯛やタラで年越しを祝うところもあります。
除夜の鐘

大晦日の夜のことを除夜といい、除夜から新年にかけて、各地の寺院で108つの鐘が撞かれます。108つの鐘が撞かれるのは、人間の心をまどわす煩悩が108あるからという説が有名ですが、ほかにも暦の12ヶ月と二十四節気、七十二候を足した数という説もあります。また、寺院によっては鐘の数が108つを超えるところもあります。
コラムを探す
新着コラム
最終更新日 2025年4月1日
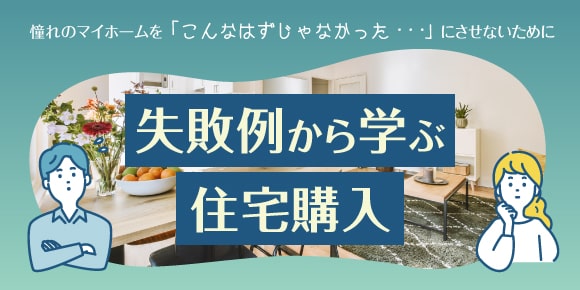
- マイホームは、多くの人にとって一生に一度の高額な買い物。住んでから「こんなはずじゃなかった」と頭を抱えることがないよう、どんな点に注意すればよいかを失敗例から確かめましょう。

- ある日、突然起こる家の中のトラブルや生活の困り事。水漏れ、カギ紛失、害虫が出た…など、緊急時の対応や注意点、日頃からできる備えについて紹介します。

- 庭やアウトドアリビングのある家づくりで知っておきたい基礎知識をまとめました。これから家を建てる方は必見です!
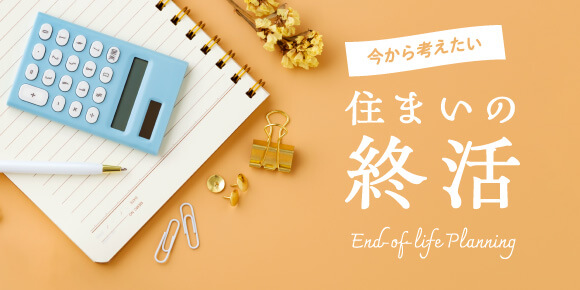
- 「終活」とは、自分らしい最期を迎えるための準備活動のこと。持ち家がある場合は、自宅の相続のことも頭に入れておきたいもの。もしものときに備えて「住まいの終活」を始めませんか。
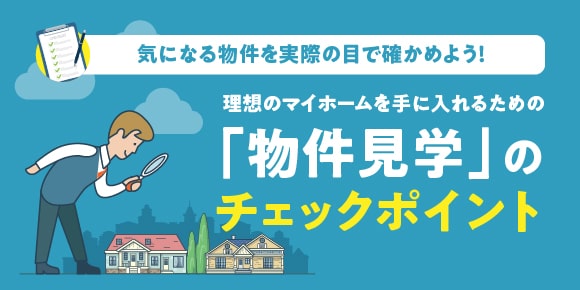
- 購入を検討している物件を現地でチェックする「物件見学」は、家探しの重要なステップの一つ。物件見学時にきちんと確認したいポイントを押さえて、家選びを成功させましょう!

- 災害は、ある日突然やってきます。いざというときにペットと自分を守れるように、飼い主さんができる「日頃の備え」と「災害時の行動」を学んでいきましょう。
- 住まいの情報ナビ
- 趣味やライフスタイル
- 家族や友人と楽しむ身近な年中行事!
- 12月の行事 大晦日 12月31日



