2015年11月28日 更新
![]()
![]()
マイホームを取得したら、いよいよ新生活の始まりです。新居の楽しみはいろいろありますが、万一の不具合などのトラブルや、維持費などについてもきちんと把握しておきましょう。
![]()
 引渡し前にチェックを行っているとはいえ、住宅の不具合や欠陥は、実際に住んでから気付くケースが少なくありません。もしも新居で不具合が見つかったら、早めに売主に修理を依頼しましょう。売買物件は多くの場合、売主がアフターサービスを設けており、一定期間内であれば無料で補修を受けることができます。サービスの期間や適用基準は売主によりさまざまですから、あらかじめ契約時に確認しておきましょう。
引渡し前にチェックを行っているとはいえ、住宅の不具合や欠陥は、実際に住んでから気付くケースが少なくありません。もしも新居で不具合が見つかったら、早めに売主に修理を依頼しましょう。売買物件は多くの場合、売主がアフターサービスを設けており、一定期間内であれば無料で補修を受けることができます。サービスの期間や適用基準は売主によりさまざまですから、あらかじめ契約時に確認しておきましょう。
中には施工ミスや工事の手抜きなどが原因で、雨漏りやシロアリ被害などの重大な欠陥が見つかることもあります。このような場合は、法律により「瑕疵担保責任」が適用されます。
瑕疵担保責任とは、物件の引渡し後に隠れた欠陥(瑕疵)があった時に、買い手側が売主に対して無料の修理を求めたり、損害賠償を請求したりすることができるものです。
瑕疵担保責任の適用は、新築なら引渡しから10年以内なら保証の期間とされています。中古なら契約内容にもよりますが、売主が宅建業者(不動産会社など)なら2年以上、個人の場合は半年以内の保証期間が設けられている場合がほとんどです。
![]()
マイホームをいい状態に保つには、日頃のチェックやメンテナンスが欠かせません。マンションなら管理会社が共用部分の点検・メンテナンスを定期的に行ってくれますが、戸建ては日頃から居住者みずからチェックを行い、傷みや劣化などがあれば早めに対処することが大切です。
![]()
| 屋根 | スレート屋根の色あせがないか |
| 金属屋根のサビつきや色あせがないか | |
| 瓦やスレートが割れたりズレたりしていないか | |
| 雨どいが詰まったり破損したりしていないか | |
| 屋根 | 外壁の表面を手でこすると、手に塗装の粉が付着しないか |
| 外壁材のつなぎ目の部分にヒビ割れやはがれがないか | |
| モルタルにはがれやヒビ割れがないか | |
| バルコニー | 排水口が詰まって水切れが悪くなったり破損したりしていないか |
| 家とバルコニーの間に隙間ができていないか | |
| 防水が劣化していないか | |
| 水まわり | カビが発生していないか |
| タイルの欠けやヒビ割れがないか | |
| 床下にシミができていないか | |
| 水漏れが起きていないか | |
| 床 | 床材のキズや凹みはないか |
| 歩くとフワフワと足が沈む部分がないか | |
| ビニル系床がはがれてめくれ上がっていないか | |
| 外まわり | 木部の塗装がはがれていないか |
| 鉄部にサビが発生していないか | |
| 塀の傾きやヒビ割れがないか |
※住宅の劣化しやすいポイントと対処については「住宅の劣化しやすい部分とは?」を参照
![]()
マイホームの取得後にかかるお金は、毎月の住宅ローンの返済以外にも、維持管理費や保険料、税金などが発生します。特に税金は納税通知書が届いてから慌てることがないように、いつ、どんな納税があるか、軽減措置はあるかなどをチェックしておきましょう。
![]()
| 住宅の維持管理費 | |
|---|---|
| 管理費 (マンション) | マンションの維持管理のために、毎月発生する費用。金額はマンションにより異なるが、修繕積立金と合わせて月額2万円前後が目安 |
| 修繕積立金 (マンション) | マンションの長期修繕計画にもとづいて、毎月積み立てる費用。金額はマンションにより異なるが、管理費と合わせて月額2万円前後が目安 |
| 修繕費 (戸建て) | 戸建ての場合、マンションのような管理費や修繕積立金は発生しないが、日々の補修や将来のリフォームに備えて年間10~20万円程度積み立てておくとよい |
| 保険料 | |
| 団体信用生命保険料 | 住宅ローンの借入れを行った人が死亡したり高度障害になったりした時に、ローンの残金を完済する保険で、住宅ローンを組むなら強制加入であることがほとんど。保険料はローン残高によって決まり、目安は年額0円~10万円程度 |
| 火災保険料 | 住宅ローンを組む場合は強制加入。保険料は保証内容により異なるが、目安は年額1~2万円程度 |
| その他の保険料 | 必要に応じて、上記の火災保険に家財保険や地震保険をプラスすることも可能 |
| 駐車場代 | |
| 駐車場代 | マンションや、戸建てでも外部の駐車場を利用する場合に発生。金額は地域差が大きく、月額数千円~数万円かかる |
| 税金 | |
| 不動産取得税 | 土地や建物を取得した際に1度だけかかる税金※税額の計算方法などは下記を参照 |
| 固定資産材 | 土地や建物を所有していると毎年かかる税金※税額の計算方法などは下記を参照 |
| 都市計画税 | 市街化区域に土地や建物を所有していると毎年かかる税金※税額の計算方法などは下記を参照 |
![]()
マイホームの取得後にかかる税金には「不動産取得税」「固定資産税」「都市計画税」があります。これらの税金は自治体の条例により要件や税率が異なる場合があるため、詳細は物件の所在地の自治体にお問い合わせください。
![]()
土地や住宅用の建物を取得した際に1度だけかかる税金で、2018年3月31日までに取得した場合は以下の軽減税率が適用されます。
![]()
不動産評価額×3%(税率) ※土地や住宅用の建物の場合
また、下記の基準を満たした物件であれば、建物は不動産評価額から、土地は不動産取得税から控除が受けられます。この控除を受けるには、各都道府県の税務署への申告が必要です。
| 新築の場合(増改築を含む) |
|---|
|
要件……床面積が50~240㎡の物件 控除額……不動産評価額から1,200万円(長期優良住宅(※)の場合は1,300万円)の控除 ※長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態を保てるよう耐震性や省エネ性などの項目において認定基準に適合した住宅のこと |
| 中古の場合 |
|---|
|
要件……床面積が50~240㎡、1982年1月1日以後に新築された物件で耐震基準に適合したもの 控除額……新築された年月日に応じて、不動産評価額から100万~1,200万円の控除 |
| 住宅用に取得した土地の場合 |
|---|
|
要件……次のいずれかに該当していること ・土地の取得後3年以内に住宅が新築されている ・住宅の新築後1年以内にその土地を取得 ・新築で未使用の住宅とその土地を、新築後1年以内に同じ人が取得
控除額…次の(1)(2)のうち、高いほうの金額を不動産取得税から控除 |
![]()
土地や建物を所有しているとかかる税金で、毎年1月1日の時点で固定資産税台帳に登録されている人に、自治体から納税通知書が届きます。
![]()
不動産評価額×1.4%(税率)
また、下記の基準を満たした物件には固定資産税の軽減措置があります。
| 住宅用の土地の場合 |
|---|
|
要件と軽減額… 土地面積のうち200㎡以下の部分 → 課税標準額が不動産評価額の6分の1に 土地面積のうち200㎡以上の部分 → 課税標準額が不動産評価額の3分の1に (ただし建物の床面積の10倍が上限) |
| 新築の場合 |
|---|
|
要件……2016年3月31日までに新築された住宅で、居住用の床面積が2分の1以上で、その床面積が50~280㎡のもの 軽減額……以下の期間にわたって、床面積の120㎡までは固定資産税が2分の1に 3階以上の耐火・準耐火構造の住宅 → 新築後5年間 上記以外の住宅 → 新築後3年間 |
| 新築の長期優良住宅の場合 |
|---|
|
要件……2016年3月31日までに新築された長期優良住宅 軽減額……新築後5年間(マンションの場合は新築後7年間)は固定資産税が2分の1に |
![]()
市街化区域に土地や建物を所有しているとかかる税金で、毎年1月1日の時点で固定資産税台帳に登録されている人に、自治体から納税通知書が届きます。
![]()
不動産評価額×最高0.3%(税率)
また、下記の基準を満たした物件には固定資産税の軽減措置があります。
| 住宅用の土地の場合 |
|---|
|
要件と軽減額…… 土地面積のうち200㎡以下の部分 → 課税標準額が不動産評価額の3分の1に 土地面積のうち200㎡以上の部分 → 課税標準額が不動産評価額の3分の2に (ただし建物の床面積の10倍が上限) |
![]()
2019年6月30日までに住宅ローンを利用してマイホームを取得し、取得から6ヶ月以内に入居すると、年末のローン残高に応じて所得税額から一定額の控除が受けられます。この控除を受けるためには、マイホームを取得した翌年の2月16日から3月15日の間に税務署に確定申告をします。
![]()
住宅ローンの年末残高×1%
控除の要件や対象となるローンの残高上限などは次のとおりです。
|
主な要件…… ・住宅の床面積が50㎡以上 ・中古の場合、木造なら築20年以内、マンションなどの耐火建造物は築25年以内 ・ローンの借入れ期間が10年以上 ・所得が3,000万円以下
控除の対象となるローンの残高上限…… ※低炭素住宅とは、住宅からのCO2排出を削減するために省エネ性や断熱性などの項目において認定基準に適合した住宅のこと |

マイホーム取得までの道のりは、理想が少しずつ現実になっていくようすを家族で実感できるチャンス。
やるべきことが多くて大変なこともありますが、うまくポイントを押さえて効率よく進めていきましょう。
コラムを探す
新着コラム
最終更新日 2025年4月1日
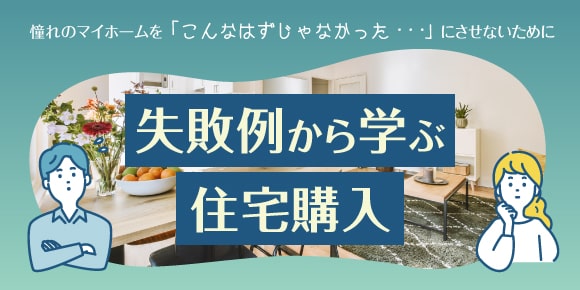
- マイホームは、多くの人にとって一生に一度の高額な買い物。住んでから「こんなはずじゃなかった」と頭を抱えることがないよう、どんな点に注意すればよいかを失敗例から確かめましょう。

- ある日、突然起こる家の中のトラブルや生活の困り事。水漏れ、カギ紛失、害虫が出た…など、緊急時の対応や注意点、日頃からできる備えについて紹介します。

- 庭やアウトドアリビングのある家づくりで知っておきたい基礎知識をまとめました。これから家を建てる方は必見です!
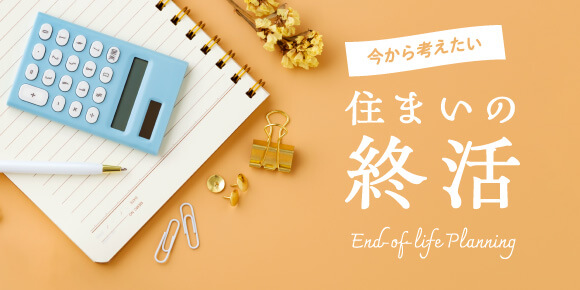
- 「終活」とは、自分らしい最期を迎えるための準備活動のこと。持ち家がある場合は、自宅の相続のことも頭に入れておきたいもの。もしものときに備えて「住まいの終活」を始めませんか。
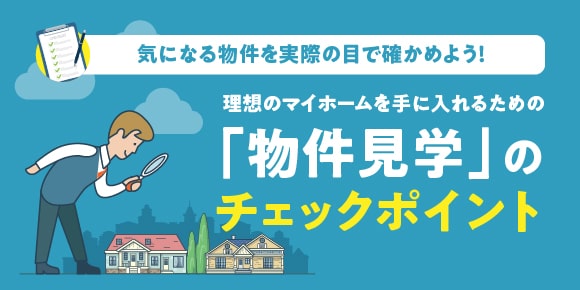
- 購入を検討している物件を現地でチェックする「物件見学」は、家探しの重要なステップの一つ。物件見学時にきちんと確認したいポイントを押さえて、家選びを成功させましょう!

- 災害は、ある日突然やってきます。いざというときにペットと自分を守れるように、飼い主さんができる「日頃の備え」と「災害時の行動」を学んでいきましょう。



