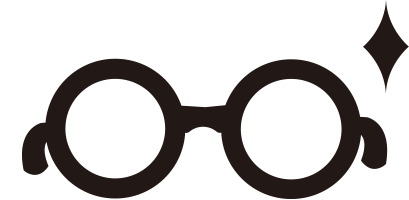マイホームの庭づくりを成功させるコツ

どんなに立派な建物を建てても、庭が殺風景だったり、庭で過ごす機会がない、または除草などの手間ばかりかかる庭だと、後悔や不満につながります。家族みんなが庭のある家を最大限に楽しむために、庭を計画する際のポイントを紹介します。
庭づくりのプランで大切なことは?
明庭でやりたいことを明確にするとプランを立てやすい

庭を計画する際に、必ず考えておきたいのが「庭をつくる目的や用途をあきらかにすること」。
たとえば、花や緑の景色を観賞するなら、リビングなどから見える場所に花壇や植栽を配して、四季折々の表情を楽しめるようにします。また、子どもやペットがのびのびと走り回れる庭をつくるなら、ある程度の広さを確保した上で、コンクリートや砂利敷きは避け、クッション性の高い芝生を全面に張る必要があるでしょう。
このように目的や用途をはっきりさせることで、庭のデザイン、必要な広さ、使用する素材・設備など、庭づくりの方向性が決まってきます。
目的や用途を定めずに「とりあえず」庭をつくったものの、結局は庭を使用せず、見向きもしない…なんて状況は避けたいですよね。せっかく庭をつくるのですから、家族みんなの満足度を高め、暮らしを豊かにする庭を実現しましょう。
必要な予算は?
敷地の広さやこだわりに応じて予算はまちまち

庭を含む建物の外まわりを整える外構工事費用は、一般的に本体工事費用の10~15%程度が目安といわれています。
ただし、実際にどれくらいの金額になるかは、敷地の広さ、植栽の範囲、使用する素材・設備などによってケースバイケース。素材・設備はグレードやこだわりに応じて価格帯もさまざまですし、敷地が広いほど、境界フェンスや芝生などの舗装面積も増えるため、金額がかさみがちです。
【庭づくりのコストの目安】
- ・フェンス設置 数千円~5万円/m
- ・生垣の植栽 5000円~/m
- ・樹木の植栽(1.5m前後の中木) 2万円~
- ・芝生張り 5000円~/㎡
- ・コンクリート舗装 1万5000円前後/㎡
- ・ウッドデッキ設置 4万円~/㎡
建物同様、庭づくりのコストもこだわればキリがないので、全体の予算のバランスを見ながら無理のない金額を設定しましょう。初期導入コストはもとより、住んでからの維持管理コストを考えておくことも大切です。
必要な広さは?
庭づくりの目的や用途から広さを決定する

狭すぎる庭は活用が難しく、広すぎる庭はお手入れが大変です。我が家にとってちょうどよい庭の広さを考える際は、庭づくりの目的や用途を基準にするとよいでしょう。
具体的にいうと、庭でガーデニングや家庭菜園をするなら、1坪(約2畳)前後の広さがあれば十分です。子どもの遊び場として使用する場合や、ガーデンチェアやテーブルを並べてBBQなどを楽しむ場合は、3坪(約6畳)以上あると使い勝手がよくなります。
敷地内に庭を配置する際は、まず建物と駐車スペースの配置を決めて、それ以外のスペースを庭などにあてることになります。実際の配置図を見ながら、庭の広さはもとより、奥行や、建物との動線なども確認しておくことをおすすめします。
庭づくりの依頼先はどうする?
建物の依頼先か、外注か。それぞれの特徴をチェック!

庭を含む外構工事を、どこに依頼するかも決めておきましょう。
外構工事は基本的に、
(1)建物をつくるハウスメーカーや工務店に依頼する場合
(2)外部業者に依頼する場合
の2通りがあります。
(2)の外部業者については、主に外構工事全般を行う外構業者と、庭づくりが専門の造園業者に大きく分かれます。ただし、外構メインでも庭木や草花に明るい会社、造園メインでも外構を手掛ける会社もあり、業者ごとに得意分野やカバーする範囲が異なるため、事前にHPなどでリサーチしておくと安心です。
(1)建物をつくる業者に依頼する場合
ハウスメーカーや工務店に依頼する場合のメリットとして、建物と外構の工事を同じ業者が手掛けるため、外観との一体感があるデザインが期待できます。工事の打ち合わせも、窓口が一本化されることで、スムーズに進めやすいでしょう。
一方デメリットとして、マージンの発生によって庭づくりの工事費が割高になりがちです。また、提案された庭のデザインやテイストが、自分の好みに合わない可能性もあります。
(2)外部業者に依頼する場合(外構業者・造園業者)
外部業者に依頼する場合、自分好みの庭に仕上げてくれる業者を選べることや、中間マージンが発生しないので、工事費を安く抑えやすいことなどのメリットがあります。
その一方で、自分で業者を探したり、建物工事の打ち合わせとは別に外構工事の打ち合わせを行ったりする手間が増えるデメリットもあります。なお、外部業者に依頼する場合、外構工事に着手できるのは建物の引き渡し後になります。
プライバシーや防犯の対策は?
家族が安心して暮らすために、しっかりと検討しておく

屋外空間である庭は、外からの視線や、侵入者などが気になります。プライバシーや防犯の対策を徹底して、家族の安心を守りましょう。
庭のプライバシー対策
庭(主庭)は日当たりのよい南側に配置するケースが多いため、南側道路に接する敷地だと、道路から庭が丸見えになることも。さらに隣家の窓の位置によっては、お互いの目が気になって、ゆっくりくつろげない可能性もあります。
とはいえ、高い塀などで庭を囲んでしまうと圧迫感や閉鎖的なイメージを感じやすく、周囲の死角になるので、防犯の面でも心配です。適度に開いた印象を与えつつ、気になる箇所に目隠しフェンスや生垣を配置して、道路や隣家からの目線を外すとよいでしょう。
庭の防犯対策
空き巣や泥棒は人目につくことを恐れるので、侵入経路となる庭などの視認性を高めることが有効な対策となります。
具体的に、庭を囲む塀やフェンスは低くするか、穴あきのパンチングフェンスや半透明のポリカーボネート製フェンスなど、適度なプライバシーを確保しながら見通しをよくするものを設置しましょう。生垣も、枝や葉の隙間から中が見えるのでおすすめです。
このほか、踏むとジャリジャリ音が鳴る防犯砂利を敷いたり、夜間に人が近づくと点灯するセンサーライト、防犯カメラを分かりやすい位置に設置したりするのもよいでしょう。
地面の素材選びは?
庭の広い面積を占める地面だからこそ、素材は慎重に選びたい

地面の土がむき出しのままだと、雑草がぼうぼうに生えたり、雨の日のぬかるみ・泥ハネが建物を汚したりして、住まいの美観が損なわれます。
そこで必要となるのが、地面部分を覆う芝生や砂利といった素材です。庭を眺めたときに、視界の大部分を占める地面部分を芝生にするか、それとも砂利にするかで、庭の印象は大きく変わってきます。
庭の地面の素材選びは、メンテナンス性にも直結します。見た目はもちろん、導入コストやお手入れのことも考えて、我が家に合った素材を選びたいものです。
芝生(天然芝)

芝生は見た目が美しい上、日光の照り返しを和らげる効果や、柔らかなクッション効果があるので、子どもやペットが思いきり走り回っても安心です。
導入コストも安価ですが、定期的な水やりや除草、芝刈りなどお手入れやメンテナンスが欠かせません。
人工芝

合成樹脂製の人工芝は、天然芝と違って枯れたりせず、水やりや除草などのお手入れも不要。耐用年数が約10年と長く、ほぼメンテナンスフリーできれいな緑が楽しめます。
芝の色や、踏み心地にかかわる長さなどの種類が豊富で、天然芝そっくりの見た目や質感のものもあります。導入コストは、天然芝よりも高めです。
砂利や砕石

「砂利」は自然の力で丸くなった小さな石、「砕石」は岩石を人工的に砕いたものを指します。
どちらも石粒の色・サイズ・丸みなどでさまざまなバリエーションがあり、庭のイメージや好みに合わせて選びやすいこと、安価で初心者でも扱いやすいことから、DIYでも人気の高い素材です。導入の際は、雑草を防ぐために地面に防草シートを敷き、その上に砂利や砕石を敷くとよいでしょう。
コンクリート

耐久性と強度にすぐれたコンクリートは、シンプルモダンなテイストの庭や、駐車スペースを兼ねた庭などに採用されることが多い素材です。
雑草の心配もなく、維持管理の手間はかかりませんが、導入時はもとより撤去の際もコストがかかります。また、庭一面がコンクリートだと味気ない印象になりがちなので、芝生などを組み合わせて温かみを出すことも検討しましょう。
レンガ

粘土や頁岩などを混ぜて型に入れ、窯で焼き固めたものがレンガです。洋風やナチュラルなカントリー風の庭、アプローチなどの通路部分に使用されることが多く、さまざまなサイズや色、質感のものがあります。
レンガの敷き方のパターンも豊富なので、好みのパターンを選んで表情豊かに仕上げることができます。
タイル

耐久性にすぐれた屋外用のタイル(ガーデニングタイル)です。
天然石や陶器、木調、大理石調、テラコッタ調など素材が豊富で、色なども多彩。タイルを庭に置くだけのタイプや、複数のタイルを連結されるジョイントタイプのものなどはDIYでも人気です。
庭木・シンボルツリー選びは?
植えたい樹木の特徴・用途・お手入れなどを考えて選ぶ

庭木があれば、室内からの眺めがよくなるのはもちろん、夏の日差しを遮る日除け効果や、外から家の中が見えないようにする目隠し効果も期待できます。樹種によって、サイズや樹形、花や葉の色・形などがさまざまなので、樹木の特徴や、庭づくりの目的や用途、お手入れのことなども考えながら、気に入った樹種を選びましょう。
常緑樹か落葉樹かで選ぶ
樹木を大きく分けると、一年中緑の葉が茂る「常緑樹」と、冬になると葉を落として休眠する「落葉樹」があります。
常緑樹は一年を通して緑の景観を楽しめますが、季節感はそれほど感じられません。一方、落葉樹は夏の青葉や秋には紅葉など、季節ごとの表情を感じられますが、紅葉した後の落ち葉の掃除は大変ですし、冬の枯れ木は寂しい印象になりがちです。
常緑樹と落葉樹のどちらを選ぶかで、見た目のイメージやお手入れの頻度が変わってくるため、その家に住む人の好みやライフスタイル、庭木の用途などを考えて決めるようにしましょう。
庭の環境に合った樹種を選ぶ
地域の気候風土や、庭の土壌や日照条件に合った樹種を選ぶことで、庭木が健康に育ち、お手入れやメンテナンスもしやすくなります。
地元の造園業者や園芸店に相談すると、地域の特性に応じたおすすめの樹種を教えてもらえます。
用途に応じて選ぶ
鑑賞用の庭木やシンボルツリーなら見た目で選んでも構いませんが、目隠しのために植えるなら、一年を通して葉が落ちない常緑樹がおすすめです。また、夏に木陰をつくるなら、高木で日差しに強い樹種がよいでしょう。ほかにも「生垣をつくる」「実を収穫する」など、庭木の用途や目的を考えて樹種を選ぶようにします。
お手入れのことを考えて選ぶ
庭木は植えたら終わりではなく、日常の水やりや剪定、病害虫対策、落ち葉掃きといったお手入れが発生します。これらの負担を少しでも減らすには、なるべく手間のかからない樹種を選ぶのがポイントです。
たとえば、剪定を少なくするなら、成長の遅い樹種や、樹形が自然と整う樹種を選びます。また、秋の落ち葉掃きの手間を減らしたい場合は、落葉樹を避けて常緑樹を選びましょう。手間のかからない樹種選びやお手入れについては、造園業者や園芸店などで相談できます。
 まとめると…
まとめると…
世界で1つの庭づくりを実現。不安や疑問があればプロに相談を!

庭は一つとして同じものはなく、その家の敷地の状況や、住んでいる家族の希望やライフスタイルなどによって、求められる広さや素材選びなども変わってきます。
理想とする庭のイメージが、予算などの都合で実現が難しくても、ハウスメーカーや工務店、庭づくりの専門業者に相談すれば、プロの視点で代わりのアイデアを提案してもらえる場合があります。自分にとって最高の庭をつくるために、不安や疑問があれば気軽に相談しましょう。
コラムを探す
新着コラム
最終更新日 2025年4月1日
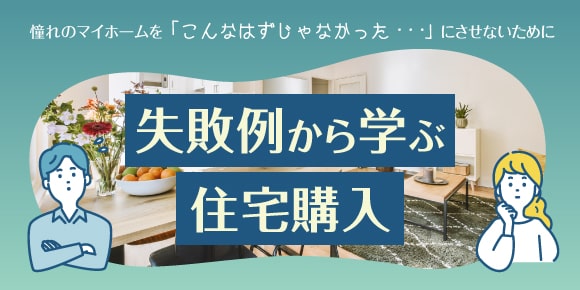
- マイホームは、多くの人にとって一生に一度の高額な買い物。住んでから「こんなはずじゃなかった」と頭を抱えることがないよう、どんな点に注意すればよいかを失敗例から確かめましょう。

- ある日、突然起こる家の中のトラブルや生活の困り事。水漏れ、カギ紛失、害虫が出た…など、緊急時の対応や注意点、日頃からできる備えについて紹介します。

- 庭やアウトドアリビングのある家づくりで知っておきたい基礎知識をまとめました。これから家を建てる方は必見です!
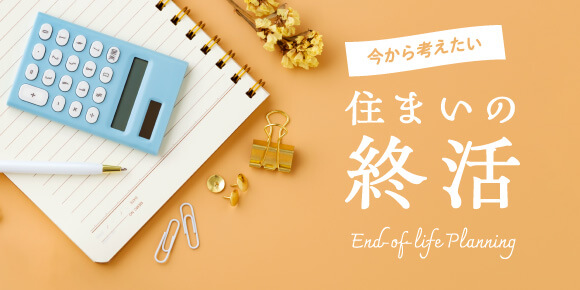
- 「終活」とは、自分らしい最期を迎えるための準備活動のこと。持ち家がある場合は、自宅の相続のことも頭に入れておきたいもの。もしものときに備えて「住まいの終活」を始めませんか。
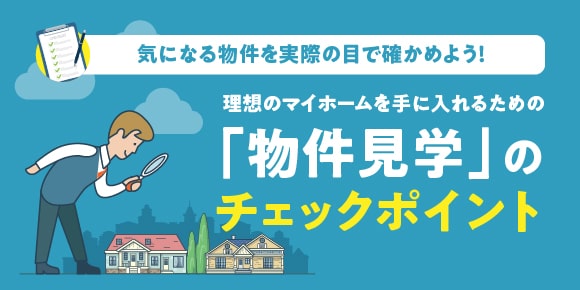
- 購入を検討している物件を現地でチェックする「物件見学」は、家探しの重要なステップの一つ。物件見学時にきちんと確認したいポイントを押さえて、家選びを成功させましょう!

- 災害は、ある日突然やってきます。いざというときにペットと自分を守れるように、飼い主さんができる「日頃の備え」と「災害時の行動」を学んでいきましょう。
- 住まいの情報ナビ
- 住まい探しのコツや建物の知識
- 住まいの楽しみが広がる!庭・アウトドアリビングのある家で暮らす
- マイホームの庭づくりを成功させるコツ