2018年9月5日 更新

![]()
かつては、未就学児の子どもを預ける施設といえば幼稚園か保育園でしたが、2006年に認定こども園の制度が始まり、選択肢が増えるようになりました。
行政的には、幼稚園は文部科学省が管轄する「学校」で、保育園は厚生労働省が管轄する「児童福祉施設」と区別されています。認定こども園は、園によって学校タイプや児童福祉施設タイプ、その両方のタイプがありますが、内閣府が管轄し、文部科学省や厚生労働省とも連携をはかっています。
また、子どもを預ける保護者の立場からすると、幼稚園と保育園は「母親が働いているかどうか」が利用の分かれ目と考える方も多いと思います。
確かに、もともと幼稚園は専業主婦世帯の子どもが通う施設として、保育園は共働き世帯の子どもが通う施設としてつくられたものですが、現在、保育園などを利用する場合に必要とされる「保育認定」では、保護者の就労以外にも妊娠・出産、病気、介護といった事情があれば認定が受けられる仕組みになっていますし、共働き世帯でも子どもを幼稚園に預けるケースもみられます。
認定こども園の場合、保護者の就労の有無にかかわらず子どもを預けることができます。
- 幼稚園・保育園・認定こども園の基本的な違い
| 幼稚園 | 保育園(認可保育園) | 認定こども園 | |
|---|---|---|---|
| 所管 | 文部科学省 | 厚生労働省 | 内閣府が管轄するが、文部科学省や厚生労働省とも連携 |
| 法的な位置づけ | 学校 | 児童福祉施設 | ※園により異なる 幼保連携型の場合は、学校かつ児童福祉施設 |
| 対象年齢 | 3才~小学校入学前まで | 0才~小学校入学前まで | 0才~小学校入学前まで |
| 利用できる認定区分★ | 制限なし | 2号・3号認定(★) | 1号・2号・3号認定(★) |
| 保育料 | ※園により異なる | 世帯の収入に応じて自治体が定めた負担額 | 世帯の収入に応じて自治体が定めた負担額 |
| 保育時間の目安 | 4時間(教育標準時間) | 11時間(保育標準時間) または8時間(保育短時間) | 1号(★)の場合は4時間(教育標準時間) 2号・3号(★)の場合は11時間(保育標準時間) または8時間(保育短時間) |
| 保育者の資格 | 幼稚園教諭 | 保育士 | ※園により異なる 幼保連携型の場合は保育教諭(幼稚園教諭と保育士の両方の資格を持つ者) |
| 給食の提供 | 任意 | 義務 | 1号(★)の場合は任意 2号・3号(★)の場合は義務 ※地域や園により異なる場合あり |
★認定区分(1号・2号・3号)って?
2015年に、子育てを支える新しい仕組みとして「子ども・子育て支援新制度(以下、「新制度」と表記します)」がスタートしました。
新制度のもとにある幼稚園・保育園・認定こども園などの施設の利用を希望する場合、お住まいの自治体から認定を受ける必要があります。
認定は、子どもの年齢や「保育を必要とする事由(※下記参照)」によって1号・2号・3号の区分に分けられます。
※保育を必要とする事由とは…
○就労(フルタイム・パートタイム・夜間・居宅内の労働など)○妊娠・出産 ○保護者の病気や障害 ○親族の介護・看護 ○罹災 ○求職活動中 ○就学や職業訓練中 ○虐待やDVのおそれがあること ○育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること…など
![]()
・子どもが0~2才まで
| 保育を必要とする事由に当てはまる | 3号認定 (保育認定) | 利用できる施設は… ・保育園 ・認定こども園 | |
| 保育を必要とする事由に当てはまらない | 認定は受けられませんが、必要に応じて一時預かり保育などを利用できます ※一時預かり保育については「情報収集・見学のコツ」で紹介します | ||
・子どもが3才~小学校入学前まで
| 保育を必要とする事由に当てはまる | 2号認定 (保育認定) | 利用できる施設は… ・保育園 ・認定こども園 | |
| 保育を必要とする事由に当てはまらない | 1号認定 (教育標準時間認定) | 利用できる施設は… ・保育園 ・認定こども園 |
コラムを探す
新着コラム
最終更新日 2025年4月1日
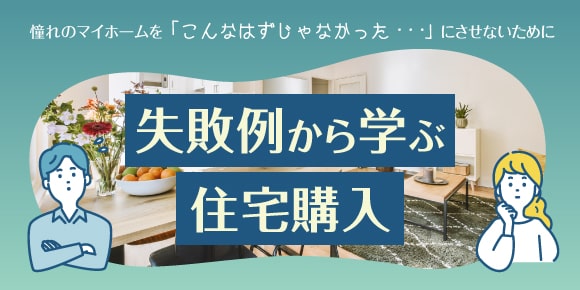
- マイホームは、多くの人にとって一生に一度の高額な買い物。住んでから「こんなはずじゃなかった」と頭を抱えることがないよう、どんな点に注意すればよいかを失敗例から確かめましょう。

- ある日、突然起こる家の中のトラブルや生活の困り事。水漏れ、カギ紛失、害虫が出た…など、緊急時の対応や注意点、日頃からできる備えについて紹介します。

- 庭やアウトドアリビングのある家づくりで知っておきたい基礎知識をまとめました。これから家を建てる方は必見です!
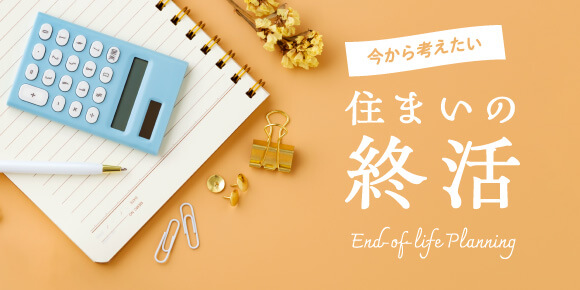
- 「終活」とは、自分らしい最期を迎えるための準備活動のこと。持ち家がある場合は、自宅の相続のことも頭に入れておきたいもの。もしものときに備えて「住まいの終活」を始めませんか。
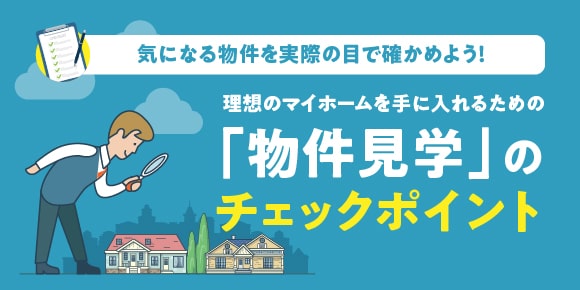
- 購入を検討している物件を現地でチェックする「物件見学」は、家探しの重要なステップの一つ。物件見学時にきちんと確認したいポイントを押さえて、家選びを成功させましょう!

- 災害は、ある日突然やってきます。いざというときにペットと自分を守れるように、飼い主さんができる「日頃の備え」と「災害時の行動」を学んでいきましょう。



