2014年11月25日 更新
![]()
![]()
そもそもご近所さんとは“お互いの家が近いという条件でつながった関係者”です。家が近いというだけで年齢、立場、家族構成などはさまざまですから、考え方や生活習慣が異なるのは当たり前。それが同じ地域に暮らすとなると、時にはトラブルに発展することがあるかも知れません。
けれども、トラブルが起きたからといって簡単に引っ越しなどできませんから、程よい距離感で「ご近所付き合い」をする必要があります。
![]()
![]()
もしもあなたの家の隣に誰かが引っ越してきて、夜中に物音を立てたり、人の出入りが激しかったりしたら……。きっと「どんな人たちなのだろう?」と不安で落ち着かない気分になるはずです。このような顔の見えない状況は不安が募りやすく、不安からトラブルが起きることも。普段からお付き合いをして顔見知りになっておけば、お互いの不安を解消できますし、トラブルも回避しやすくなります。
![]()
2011年の東日本大震災で、隣近所の人たちが協力して救助や避難生活を乗りきったという例をご存じの人も多いのではないでしょうか。“遠くの親戚より近くの他人”というように、万一の災害時や犯罪、病気、ケガなどの緊急時には、ご近所さんの力が大きな助けになります。特に小さいお子さんやお年寄り、体の不自由な人がいる家庭では、個人や家族だけでできることに限界があります。隣近所で助け合える体制を整えておくとよいでしょう。
![]()
ご近所さんと道ばたで会っても、無言で目をそらしてしまうのはなんとなく気まずいですよね。世間話で盛り上がる必要はありませんが、「こんにちは」と挨拶するだけで気持ちが軽くなるものです。日頃からコミュニケーションを心がけていれば、なにかあった時に気軽に声かけしやすいというメリットも。お互いに気まずくなる前に、ぜひ挨拶のコミュニケーションを始めましょう。
![]()
「地域力」とは、安全、教育、自治など地域が抱える問題に住民が関心を持ち、解決していこうとする力のこと。地域力が高い地域ほど町に活気があり、災害時の助け合いや犯罪の抑止、子育ての協力などの体制が整っているため、「住みやすい町」として人気が高まる傾向があります。そんな地域力を支える一つが、ご近所同士のコミュニケーション。ご近所付き合いが活発になれば住民の意識も高まり、地域力の強化につながります。ご近所付き合いを通して10年後、20年後も暮らしやすい魅力的な町づくりを進めましょう。
![]()
ご近所付き合いは上記のようなメリットがある一方で、どうしても面倒なことが起こるのも事実。例えば、程よい距離感のお付き合いをしたくても、中には他人のプライバシーを詮索する人がいるかも知れませんし、自治会の活動が熱心な地域では、地元のお祭りや清掃に参加するのが大変、という声も聞かれます。
コミュニケーションの得意・不得意には個人差がありますから、ご近所付き合いを苦痛に感じる人もいるでしょう。ただし、同じ地域で暮らしている以上、ある程度のお付き合いは仕方ないこと。「お付き合いのメリットもあるのだから」と割り切って、大人の対応を心がけたいものです。
![]()
もしも大震災が起こって、あなたや家族が生き埋めになったり閉じこめられたりしたら、どうやって救助をお願いしますか?
「救助隊を待つ」という選択肢もありますが、事故や火災が頻発する災害時に救助隊による救助はほとんど期待できません。実際に1995年の阪神大震災では、救助隊によって救助された人はわずか1.7%。それ以外は自力で脱出するか、家族や隣人などに救助されています(表参照)。
この阪神大震災は家族の在宅率が高い早朝に起こりましたが、東日本大震災のように、家族がバラバラに出払っている日中に地震が起こった場合、友人や隣人に救助される可能性はますます高まると考えられます。いざという時に備えて、日頃からご近所付き合いを大切にしたいですね。

コラムを探す
新着コラム
最終更新日 2025年4月1日
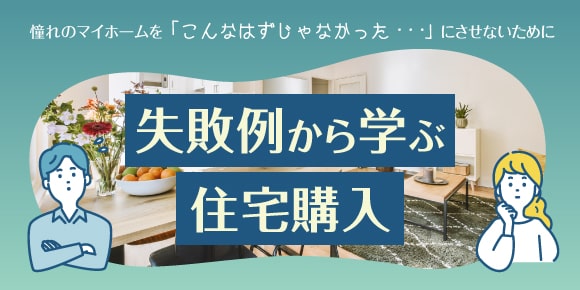
- マイホームは、多くの人にとって一生に一度の高額な買い物。住んでから「こんなはずじゃなかった」と頭を抱えることがないよう、どんな点に注意すればよいかを失敗例から確かめましょう。

- ある日、突然起こる家の中のトラブルや生活の困り事。水漏れ、カギ紛失、害虫が出た…など、緊急時の対応や注意点、日頃からできる備えについて紹介します。

- 庭やアウトドアリビングのある家づくりで知っておきたい基礎知識をまとめました。これから家を建てる方は必見です!
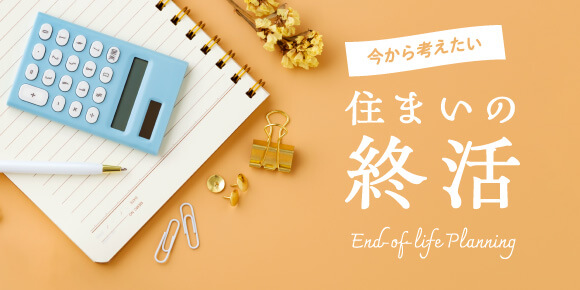
- 「終活」とは、自分らしい最期を迎えるための準備活動のこと。持ち家がある場合は、自宅の相続のことも頭に入れておきたいもの。もしものときに備えて「住まいの終活」を始めませんか。
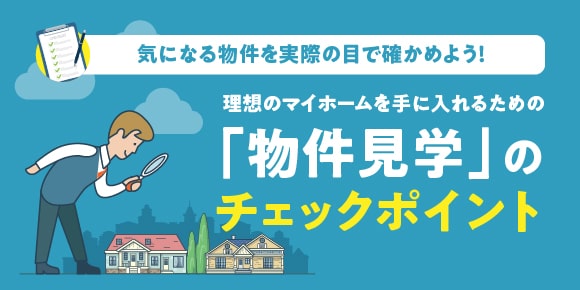
- 購入を検討している物件を現地でチェックする「物件見学」は、家探しの重要なステップの一つ。物件見学時にきちんと確認したいポイントを押さえて、家選びを成功させましょう!

- 災害は、ある日突然やってきます。いざというときにペットと自分を守れるように、飼い主さんができる「日頃の備え」と「災害時の行動」を学んでいきましょう。



