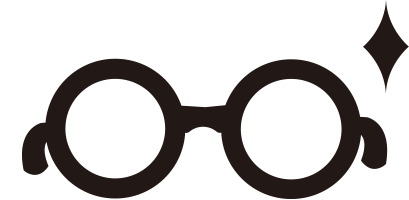「まちの中で」SDGsアクション!

私たちが暮らす地域や、お出かけ先のまちの中でSDGsのヒントが見つかることも。さらに最近はSDGsに取り組む店舗などが増えており、このような店舗を利用することもSDGsのための行動になります。通勤・通学時、近所のお散歩、休日のショッピングや外食など、できる範囲でSDGsに取り組んでみましょう。
外出時はマイバッグ、マイボトルを忘れずに
プラスチックごみを減らして海の環境を守る

◎SDGsターゲット:目標14「海」
2020年7月からプラスチック製レジ袋の有料化がスタートし、買い物のときにマイバッグを持参するようになった人も多いのではないでしょうか。このレジ袋有料化の背景には、近年増え続けるプラスチックごみが毎年800万トン以上も海に流れ込み(※)、環境汚染を引き起こしていることが挙げられます。海に流れ込んだプラスチックごみは細かい破片になり、それを鳥や魚がエサと間違えて食べてしまい、その魚を人間が食べることで人体にも影響を及ぼします。
海のプラスチック汚染を減らすためには、なるべくプラスチックごみを出さないようにすることが大事です。マイバッグだけでなく、マイボトルを持参すれば外出先でペットボトル飲料を買う機会も減ります。これからはお出かけ前の習慣として、カバンにマイバッグとマイボトルを入れましょう。
近場に出かけるなら徒歩や自転車で
CO2を排出せず、健康にも役立つ移動手段

◎SDGsターゲット:目標3「健康」、目標13「気候変動」
近年、夏がくるたびに「猛暑」や、超大型台風などの「異常気象」のニュースを目にするようになりました。その原因は、地球温暖化により海水温が上昇したためだといわれています。
地球温暖化に影響を及ぼすとされるCO2は、自動車の排気ガスなどに含まれています。現在、各国でCO2排出規制の取り組みが行われていますが、日常でも、近場に出かけるときはマイカーではなく、なるべく徒歩や自転車を利用しましょう。徒歩や自転車は環境に優しいのはもちろん、程よい運動になり健康にも役立ちます。遠出の際も鉄道やバスなどの公共交通機関をできる限り利用して、マイカー利用を控えましょう。
買いすぎを防ぐマイルールを決める
衝動買い、大量買いを避けて環境とお財布に優しく

◎SDGsターゲット:目標12「責任」、目標13「気候変動」
買い物をしていて、つい衝動的に購入した服がタンスの肥やしになっていたり、たくさん食品を買いすぎて結局食べ切れなかったり……。お店にはたくさんの商品が並んでいますが、不要なものまで買ってしまうとゆくゆくはごみとなり、処分するために大量のエネルギーを消費することになってしまいます。
ごみを減らすために買いすぎは控えて、必要なものを必要な量だけ買うようにしましょう。服は「流行に左右されないベーシックなデザインを選ぶ」、食品は「数日~1週間分のレシピを組み立ててから買う」など、自分なりのルールを決めておくと、衝動買いとお財布のムダづかい防止に役立ちます。
 ちょこっとメモ!
ちょこっとメモ!
助け合いのしるし「ヘルプマーク」について。援助や配慮をスムーズに
ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、妊娠初期の人など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人が、そのことを周囲に知らせることで援助を得やすくするためのマークです。
私たちが普段、何気なく利用している交通機関や施設も、病気や障がいによって不便に感じたり、突発的な事故などに対してとっさに対応することが難しかったりすることがあります。そのため、マークを作成した東京都福祉保健局のWEBサイトでは、「ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします」としています(※)。病気や障がいなどにかかわらず、安心して交通機関や施設を利用できるまちは、誰もが住みやすいまちといえます。自分たちの暮らすまちを、より安心して住みやすい場所にするために、助け合いの輪を広げましょう。
レストランで食べ切れない分は持ち帰る
おいしい料理を残さず食べ切るための取り組み

◎SDGsターゲット:目標12「責任」
アメリカの飲食店では、お客が食べ切れなかった料理を自宅に持ち帰るための「ドギーバッグ」と呼ばれる容器があり、食べ残しをムダにしない文化が浸透しています。
日本では衛生上の問題もあり、これまで食べ残しの持ち帰りは一般的ではありませんでしたが、数年前から食品ロスを減らすために持ち帰りサービスを導入する飲食店が増え、国も2017年に「持ち帰りには十分に加熱された食品を提供する」といったガイドラインを提示するなどして食品ロス対策を推奨しています。
また、飲食店によってはお客が食べる量を調整しやすいハーフサイズメニューを用意したり、環境に配慮してプラスチックのストローを紙製にしたりするなど、SDGsに取り組んでいることもあります。外食をするときは、このような飲食店を候補リストに加えてみてください。
災害時の避難場所や経路を確認する
家族や地域で災害に備えて、安心して暮らせるまちに

◎SDGsターゲット:目標11「まち」
いつ、どこで起こるか分からない災害。SDGsでは「災害に強く、みんなが安心して暮らせるまちをつくること」を目標に掲げていますが、安心して暮らせるまちは堤防や防波堤などの防災設備が整っていることはもちろん、そこに住む私たちが災害に備えて準備することも重要です。
例えば各市区町村では、災害による被害を予測し、その被害範囲を地図上に示した「ハザードマップ」を公開しています。このハザードマップを見ながら、家族で避難場所や経路について話し合い、実際に避難経路を歩いてみましょう。
2011年に起きた東日本大震災では、地震直後に発生した津波から逃れるために地域の人がお互いに声をかけあって避難し、避難所を運営するなどして助け合いました。「遠くの親戚より近くの他人」という言葉があるように、災害時に近隣で助け合える人間関係も大切。日頃からご近所さんに挨拶をしたり、地域の防災訓練に参加したりすることも、安心して暮らせるまちづくりにつながります。
 まとめると…
まとめると…
「ムリせず、できることから」が大切。小さな取り組みが大きな力に!

SDGsは、2030年までに今より世界をよい場所にして、持続可能な状態にするための目標です。暮らしの中で実践できるSDGsアクションはいろいろありますが、できることからムリのない範囲で構いません。どれもこれもやろうとすると重荷になってしまうので、ご自身にとって持続可能な方法で、少しずつ世界をよりよい方向に進めていきましょう。
コラムを探す
新着コラム
最終更新日 2025年4月1日
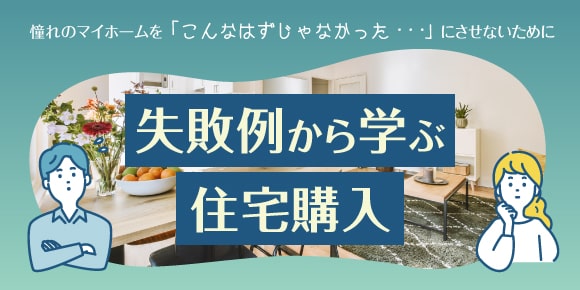
- マイホームは、多くの人にとって一生に一度の高額な買い物。住んでから「こんなはずじゃなかった」と頭を抱えることがないよう、どんな点に注意すればよいかを失敗例から確かめましょう。

- ある日、突然起こる家の中のトラブルや生活の困り事。水漏れ、カギ紛失、害虫が出た…など、緊急時の対応や注意点、日頃からできる備えについて紹介します。

- 庭やアウトドアリビングのある家づくりで知っておきたい基礎知識をまとめました。これから家を建てる方は必見です!
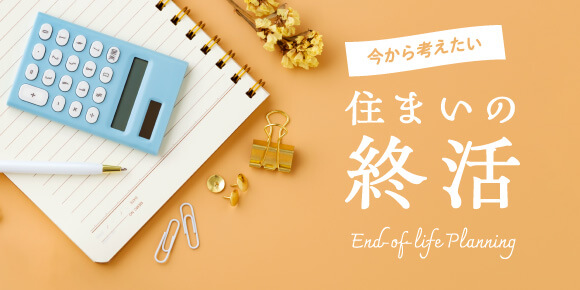
- 「終活」とは、自分らしい最期を迎えるための準備活動のこと。持ち家がある場合は、自宅の相続のことも頭に入れておきたいもの。もしものときに備えて「住まいの終活」を始めませんか。
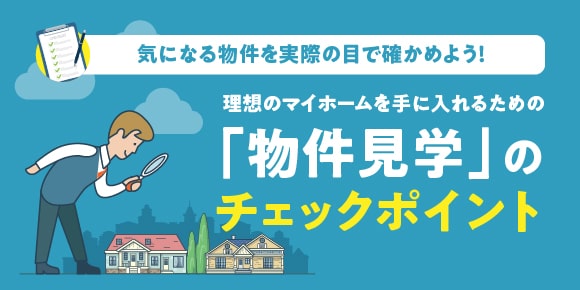
- 購入を検討している物件を現地でチェックする「物件見学」は、家探しの重要なステップの一つ。物件見学時にきちんと確認したいポイントを押さえて、家選びを成功させましょう!

- 災害は、ある日突然やってきます。いざというときにペットと自分を守れるように、飼い主さんができる「日頃の備え」と「災害時の行動」を学んでいきましょう。
- 住まいの情報ナビ
- 知って得する生活の知恵
- 暮らしの身近なSDGs
- 「まちの中で」SDGsアクション!